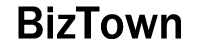- トップページ
- TMO
TMO
更新日:2024年12月01日

TMOの概要
「TMO」とは、「Town Management Organization」の略であり、日本語では「タウン・マネジメント・オーガニゼーション」と一般に呼ばれています。TMOは、地域の商業活性化、都市開発、街づくりなどを総合的に支援・推進する組織です。特に地方都市や中小規模都市において、中心市街地の集客力強化や商業環境の改善を目指しています。その背景には、人口減少や経済の停滞、都市のドーナツ化現象(中心部の衰退と郊外への人口流出)などの課題があります。TMOは、1998年に成立した「中心市街地活性化法」に基づいて設立され、この法律の目的は地方都市の中心市街地の再生と活性化を図ることです。TMOは、その具体的な実現手段として位置づけられます。これは、単なる商店街の振興に留まらず、地域全体の経済活動や生活環境の向上を目指す総合的な取り組みを示唆しています。TMOは、多岐にわたる役割と機能を持ちます。商業振興活動として新規店舗の誘致や既存店舗の改善・改装を支援し、商店街のイベントやセール、フェスティバルを企画・運営、地域産品や特産品のPR活動を行います。都市開発・再開発として空き店舗や空き地の利活用を促進し、駐車場や公共スペースの整備、建物の耐震化やバリアフリー化も推進します。また、地域独自のブランドやイメージを発信するためのマーケティング戦略を立案・実行し、観光資源や歴史文化の掘り起こしとそれを活かした観光ルートの設定も行います。住民参画とコミュニティ形成として住民や地元企業、NPOなどと協力し地域課題の解決に取り組み、地域フォーラムやワークショップを開催し意見交換や共有を促進します。さらに、環境負荷の少ない街づくりを目指し(例:グリーンエネルギーの導入、廃棄物の削減)、公共交通の利用促進や自転車の活用推進を図ります。
TMOの運営方法
TMOは、一般的には設立母体と参加者、資金調達、組織構成、評価とフィードバックという形で運営されます。設立母体は市町村や商工会議所、商店街振興組合、地元企業などが多く、多様なステークホルダーが参加することが重要であり、行政だけでなく、民間企業や市民団体も積極的に関与します。資金調達は公的資金(国や地方自治体の補助金、助成金)、民間寄付、自己資金(メンバーや参加者からの会費、協賛金)などで行われます。組織構成としては理事会や運営委員会が方針決定や主要な運営方針を決定し、事務局が日常業務やプロジェクト運営を担当、各種委員会やワーキンググループが特定の課題やプロジェクトに取り組みます。評価とフィードバックは定期的なモニタリングと評価を行い、成果を分析しフィードバックを行うプロセスで、市民や参加者からの意見を反映し柔軟に運営を改善します。福井市のTMOでは商店街の活性化を目的に設立され、市内のシャッター通りと化していた商店街に新しいカフェやアートギャラリーを誘致し、市民の交流の場を創出しました。また、地域の特産品を生かしたマーケットイベントを定期的に開催し地域ブランドの構築にも成功しています。長野県松本市のTMOは観光と商業の両面から地域振興を図る取り組みが特徴で、古い町並みを保存するとともに、新しい観光コンテンツを追加し観光客の滞在時間の延長を目指しています。地元の工芸品や食品を全国に販売するためのオンラインショップを開設し、地域産業の成長にも寄与しています。岡山県倉敷市のTMOは歴史的な街並みの魅力を維持しながら新たなビジネスを創出するための取り組みを行っています。地元の工房やギャラリーを結びつけたアートツアーを企画し、芸術文化の発信基地としての役割も果たしています。さらに、住民の声を反映させた環境に優しいまちづくりも推進しています。
TMOの課題と未来
TMOが直面する課題は多様であり、確固たる資金調達方法の確立が重要です。公的資金だけに頼るのではなく、自主財源の確保が求められ、地域住民や地元企業の参加と協力が不可欠です。そのために効果的なコミュニケーション戦略も必要です。また、持続可能な運営体制の構築も重要で、経済状況や社会環境の変化に柔軟に対応できる組織構造や方針が求められます。特にデジタル技術の進展に伴い、オンラインでの活動や情報発信も含めた総合的な対応策が求められます。結論として、TMOは地方都市や中小規模都市の中心市街地の活性化と持続可能な発展を目指すための有力な手段であり、商業振興、都市開発、地域ブランドの構築、住民参加の促進など多岐にわたる取り組みを通じて地域経済と社会の再生を図ります。今後の展開には新しい技術や手法を取り入れつつ、地域の実情に即した柔軟な対応が重要であり、多くのステークホルダーの協力が不可欠です。このような総合的なアプローチにより、TMOは地域の持続的な発展に貢献することが期待されています。