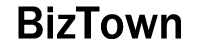- トップページ
- Do-See-Plan
Do-See-Plan
更新日:2024年12月01日

「Do-See-Plan」の定義と重要性
「Do-See-Plan」は、ビジネスや新規事業開発で用いられる一種のシステム思考またはフレームワークであり、伝統的な計画立案と実行のアプローチとは異なる動的な方法論です。このフレームワークは、「行動→観察→計画」の順に進行し、従来の「計画→実行→評価」プロセスとは逆方向にアプローチするものです。この方法は、不確実性が高く、変化の激しいビジネス環境において特に有効です。その理由と具体的なステップについて詳しく説明していきます。最初のステップは「Do(行動)」です。このフェーズでは、最初から完璧な計画立案は除外され、まずは小規模でも実際に行動を起こします。新規事業開発やイノベーションの分野では、完全な情報を持つことはほとんど不可能です。そのためには不完全な状態でも行動を開始し、実際に手を動かすことで洞察を得ることが重要です。このプロセスにおいて、失敗は許されるものであり、むしろ歓迎されます。失敗から得られる情報や知見は次のステップにおいて非常に価値あるものとなります。行動の具体例には、簡単な試作品を作成してユーザーからのフィードバックを収集するプロトタイピング、小さなマーケットや特定のターゲットに向けて商品やサービスを試験的に提供するパイロットプロジェクト、限られたリソースで新しいアイデアを実地に試す実証実験などがあります。
「See(観察)」の重要性と具体例
続いてのステップは「See(観察)」です。「Do(行動)」から得られた結果やフィードバックを詳細に観察し、データを収集します。このフェーズでは、ユーザーからの意見や感想を積極的に聴取するユーザーフィードバックの収集、使用データ、売上データ、マーケットデータなどを分析し、トレンドやパターンを把握するデータ分析、競合他社や先行している類似事業の事例を調査・分析するベンチマークなどの活動が行われます。この観察の段階で、行動の結果から得られた知見を細かく理解し、実際に何がうまくいったのか、何がうまくいかなかったのかについて視覚的かつデータドリブンに把握することが求められます。そして、最後に「Plan(計画)」のフェーズに移ります。行動と観察双方から得られた知見をもとに、新たな計画を立案します。この時点での計画は、従来の計画と比べてはるかに現実的かつ実行可能なものとなります。
計画立案の重要性と「Do-See-Plan」の応用例
計画の具体例には、具体的なアクションアイテムとタスクを洗い出す次の行動プランの策定、必要なリソース(人材、時間、予算など)を効率よく配分するリソース配分、次の行動を行う際のリスクを評価し、対策を講じるリスク管理などがあります。この計画フェーズで大切なのは、計画を柔軟にし、前回の「Do(行動)」から得られたフィードバックを積極的に取り入れることです。このプロセスを繰り返すことで、計画はどんどん精緻化され、成功の確率も高まります。「Do-See-Plan」は、迅速な行動、適切な観察、そして現実的な計画を通じて、ビジネスや新規事業開発における不確実性を減少させ、成功の可能性を高めるフレームワークです。この動的なアプローチにより、急速に変化する市場環境にも対応でき、持続的な学習と成長を促進します。柔軟で実行可能な計画を立てることで、リスクを最小限に抑えながら高い成果を追求することが可能となります。このアプローチは目標達成までの過程で低リスクを維持しつつ、高い収益性を追求することができます。試行錯誤を繰り返すことで、高確率で成功する事業の立ち上げが可能になります。応用例として、多くのスタートアップは初期段階で完璧なビジネスモデルを持たないため、「Do-See-Plan」を適用することで、市場のニーズに迅速に適応することができます。大企業においても、新規事業開発やイノベーションプロジェクトに「Do-See-Plan」を適用することで、既存の硬直したプロセスを回避し、柔軟かつ迅速に市場の変化に対応することが可能です。また、プロジェクト管理の分野でもこのフレームワークは有効です。特にアジャイル開発など、イテレーティブなプロセスが求められるプロジェクトには適しています。まとめとして、「Do-See-Plan」は、迅速な行動、適切な観察、そして現実的な計画を通じて、ビジネスや新規事業開発における不確実性を減少させ、成功の可能性を高めるフレームワークであり、持続的な学習と成長を促進します。柔軟で実行可能な計画を立てることで、リスクを最小限に抑えながら高い成果を追求することが可能となります。